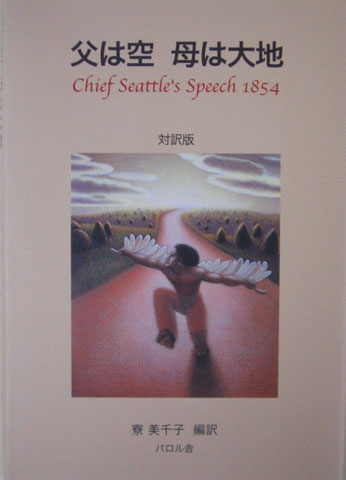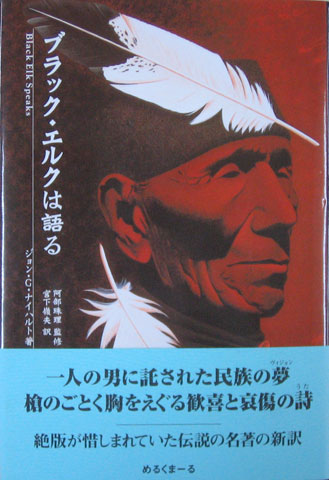 
|
猫の迷惑、人の迷惑(H.17.6.20) 猫はいつから近所の迷惑者になったのだろう。『猫にエサを与えないでください』という立看板やら貼紙の出現で、堪忍袋の口が緩みだし、区報など公の配布物にまで書かれるに至って、猫排除の動きが市民権を得てしまったことは間違いない。猫は昔からいたし、勝手気ままにどこにでも入り込み、爪を研いだり、土を掘っておしっこ、ウンチもしていたはず。丹精した庭を荒らされ、苦々しく思っていた人も今より少なかったわけではないだろう。「こらっ!!」と長箒を振り回して追い払っても懲りずにやって来る猫に、昔の人は「まったくもう。でも、まあ、猫に目くじらを立ててもねえ」と気持ちをおさめていたのだろう。 『猫にエサを与えないでください』という14文字は、猫にとっては中世の魔女狩りにも匹敵するような大変な災難だったと思う。そして、家のない猫を見過ごすことのできない人々をも、窮地に追い込むことになった。確かにエサだけあげていても問題は解決されないのだが、それにしても、エサを与えられなくなった猫がどんな姿になるのか、想像できなかったのだろうか。そんな姿の猫が町にあふれたとしても、一時のこととして目をつぶれ、と言いたかったのだろうか。区民全員が、目の前の命に目をつぶってしまえる地域など、考えるだけで恐ろしいではないか。いくら区報に書かれても、目をつぶれない人はエサをあげ続ける。お上のおふれに反する行動だから、隠れて、コソコソと。食べ終わるまで待って、後片付けすることなどできるはずもない。状況は悪化したに違いない。『猫にエサを与えないでください』の14文字の唯一の成果は、『猫害』を強く認識させてくれたことだろう。お陰で、猫たちを守りたいと思う人の心に隠れていた、「相手は猫。大目に見てくれるもの」という隣近所に対する甘えにも気づくことができた。 今でこそ、『猫にエサを与えないでください』という表現は姿を消し、猫の保護の三点セット−−エサと掃除と避妊・去勢−−を呼びかけるようになってきたが、それでも、かつて声高に訴えた14文字の禍根を拭うことはできない。禍根……それは人の堪忍袋がどんどん小さくなってきていることだ。一旦、堪忍袋から堪忍が漏れ出てしまうと、その口はなかなか塞がらず、もう堪忍を収めておくことができなくなってしまう。それは、『猫』に限ってのことではない。人は自分の回りに強固な塀を作り始め、自分と他をはっきりと区別し、自分の身の回りだけを守ることに必死になる。守る世界が狭くなればなるほど、これまで許せたことも見過ごせなくなる。 こんな状況の火付け役になっておきながら、「猫についてのトラブルは、当事者でよく話し合って解決してください」などと区報に書いて、お役所は幕引きとするつもりなのだろうか。確かに、猫は迷惑を掛ける。苦情大解禁の今は、お役所の電話も鳴り通しかもしれない。迷惑を掛ける猫&その猫を保護する人vs 迷惑を被っている区民……この加害者・被害者の構造からは、加害者側には理はないことになる。保護する側の自覚はまだ十分ではないし、啓蒙は続けていかなければならないが、それに合わせて、適切な保護活動をあたたかく見守ってもらえるような働き掛けをしてもらえないものだろうか。それくらいの罪滅ぼしはしてほしいものだ。 迷惑、迷惑、迷惑……… 猫が迷惑を掛けているなら、せめて猫を守ろうとする者は、迷惑を掛けないようにしなければならない。「猫のいるあの家、いやあねえ」などと後ろ指さされることにでもなったら、火の粉は猫に飛ぶ。空になった猫缶は、ラベルを取って中をきれいに洗い、資源ゴミとして出す。こんな当たり前のルールが妙に意識されるが、この意識がないと、いい加減になってしまうだろうことが、情けない。 私が会社の猫たちの世話をするようになって1年。ビル回りの掃除を始めて1年。最初は、猫たちを排除しようとする動きへの対抗手段の一つだった。だが、掃除は不思議な力を持っているものだ。いつしか、これみよがしな気持ちはなくなり、掃除すること自体を楽しむようになっていた。そんな私の後ろ姿に、挨拶と労いの言葉を掛けてくれる人も増えた。思い掛けない心の通い合いに、箒を持つ手はリズミカルに動き、タバコの吸い殻、缶ジュースやビールの空き缶、ガム、どこからか飛んできたチラシを次々とチリトリに運ぶ。猫の毛をはき取るつもりが、チリトリに溜まるゴミは人間が出すものばかりだ。迷惑な話だが、こうして尻拭いできるものは、まだ良いのだろう。偉そうなことを言うつもりは毛頭ない。掃除を始めるまで、ゴミのポイ捨てこそしなかったものの、足下のゴミを見て見ぬ振りを決め込んでいたのだから。 朝ご飯に没頭していた猫たちが突然飛び上がり、ビルの隙間に逃げ込んだ。隣の駐車場に車を入れようとふかしたエンジンの音だった。不必要な空ぶかしではないその音は、私には日常音。だが猫には身の危険を覚えさせる怖い音。私たちは、自分たちの文化の中にある物には、見事に順応していく。お陰で、目も耳もすっかり悪くなってしまったらしい。私たちの日常が、他の生きものに苦痛を与えていることなど、気にも留まらない。猫が飛び上がって、初めてこのエンジンの音の、ルールに収まったこの音の本質に気づく。 どこかで歯止めを掛けなければ、どこまでも身勝手に走る人間は、ルールを作った。人間の現状とすり合わせながら生まれるルールには、「やむを得ない」部分がたくさん含まれている。だが、ルールとして出来上がってしまうと、その「やむを得ない」ことまで正当化されてしまう。ルールに守られ、ときにはルールさえ犯しながら、私たちは今、同じ人間の国を海に沈めようとしている。そんな人間に、物言わぬ生きものに思いを馳せることなど、できようはずもない。理屈で分かっていても、頭で理解できても、人は五感で感じない限り、行動できないのではないだろうか。少なくとも、『鉄の意志』を持ち合わせない私にはできない。私たちはルールを作ることと引き換えに、想像力や感じる力を失ってきたのではないだろうか。 迷惑、迷惑、迷惑……それは私たち人間の存在そのもののように思える。 『自然は、子孫からの預かりもの』……たった一度どこかで聞き、以来忘れることのできなかったこの言葉がよみがえってきた。確か、インディアンの言葉だったと思う。そんな言葉を持つインディアンを知りたいと思った。机の上に分厚い本が次々と重なっていく。本屋さんに出かけてびっくりした。ネイティブ・アメリカン関連の書籍が、大きな本棚一つを占めているのだ。私をこの書棚の前に立たせたのは猫だが、多くの人がそれぞれに思うところあって、こうした書物を手に取るのだろう。 『動物記』で知られるアーネスト・シートンは、The Gospel of the Redman?an Indian Bible という本を著わしている。その巻末で、シートンは、文明の評価の尺度として15の項目を挙げ、白人の文明に酷評を与えている。6、70年も前にこのような視点を持って自己評価をし、社会に提言している人がすでにいた(インディアンの成熟した倫理・哲学については、それ以前にも多数の本が記されているが)。自分の鈍臭さにあきれるが、鈍臭いなりに五感についた錆を落とし、ネイティブ・ピープルの目で今を見てみたいと思う。全身で何かを感じたとき、何かがひとりでに変わるだろうから。 |