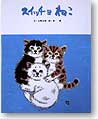|
秋の夜、やんちゃな子猫、しろきちは、スイッチョを飲み込んでしまいました。
しろきちが眠ろうとすると、いい声で鳴きはじめるスイッチョ。しろきちは、不眠症になってしまい、お医者様に行くのですが…
『スイッチョねこ』は猫を題材とした創作童話で、昭和21年10月、『こども朝日』に掲載され、猫の随筆集ともいうべき『猫のいる日々』にも収められている。
しがたって『スイッチョねこ』には、『猫のいる日々』の中で、すでに出会っていたのだが、この絵本が初対面のように感じられるのは不思議だ。というより、『猫のいる日々』の中の『スイッチョねこ』と絵本『スイッチョねこ』が独立した別個の作品に思えるのだ。
改めて『猫のいる日々』のページをめくってみた。一字一句を比べてみると、絵本は、すべてひらがなで、絵本独特の文節ごとにスペースをあける表記となってはいるものの、句読点の打ち方を含め、一字一句違いはない。確かに漢字かな送りで、文のイメージは大きく変わると思うが、一番の違いは何なのだろうか。やはり絵なのだろうか。
『猫のいる日々』の中の『スイッチョねこ』を読んだとき、頭に広がったイメージは、鎌倉の土と草の香りのする庭に煌々と照る月、広縁と障子…主人公である子猫が白猫であったことはちゃんと描かれているのに、なぜかその印象が薄かった。絵本『スイッチョねこ』の最初のページを開け、いきなり白い子猫の絵を見たその瞬間から、私にとって絵本『スイッチョねこ』は独立した作品になっていたのかもしれない。なぜだろう。猫は50年前も今も、顔形が変わるわけでもないだろうが、『猫のいる日々』を読んだ時に、私がぼんやりと描いた主人公の子猫は、もっと古風で線の細い姿をしていた。白いはずの毛も全体を覆うセピア色に染まっていた。だから、ぽやぽやとした毛に包まれた子猫特有の丸みのある体の白猫を見た途端に、『猫のいる日々』の中の『スイッチョねこ』との連続は切れたのだろう。
文体は、50年前のものだが、絵本『スイッチョねこ』は丁寧に修復した美術品のように、彩度のある作品となった。その彩度があって、初めて気付いたことがある。
それは、母猫、医者猫に対して使われ敬語、謙譲語だ。
…やさしく、なめてくださるのでした。
…だまって かんがえこんでいらっしゃるので、…
「なおりましょうか、せんせい。」と、かあさんねこが もうしました。
今、童話にこのような敬語や謙譲語が使われることは少ないような気がする。絵本『スイッチョねこ』が時代を感じさせない分、この言葉使いが目を引く。目上の人に対する敬意という、どんどん薄らいで行く概念が、50年前には、こんな童話にも当たり前のように表れていた。その言葉使いは、何ともいえない響きを持ち、そこに横たわる概念は、重く美しい。
また、全編を通して肌で感じられる季節感にもノスタルジーを覚える。
絵本『スイッチョねこ』は、私たちが失いつつあるものを、教えてくれたような気がする。
|